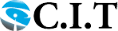一般社団法人 臨床改新協会(CIT)代表である湯田健二が、インターリハ株式会社フィジオセンター 理学療法士の田舎中(たやなか)真由美先生と「理学療法士としての自身の想いと若手理学療法士へのエール」をテーマに対談しました。
(田舎中先生)
母が看護師だったこともあり、もともと医療の道に進みたいとは考えていました。
決心したのは中学時代にバスケットボールをしていて、腰を頻繁に痛め、その時に理学療法士という仕事を知り、この仕事に就きたいと思うようになりました。
(湯田)
なるほど、早いうちから医療の道に進む決意をされ、自身の経験から理学療法を知ることになったのですね。

(田舎中先生)
出身校の大学教授の勧めで、アメリカに尿失禁の理学療法を学ぶ機会があり、その後、介護予防や高齢者の尿失禁に対して骨盤底筋群のアプローチを行っていました。
その後、自分の出産を通して明らかに変化する骨盤底筋群を実感しました。
そこから、もっと早期に予防すべきではないか、この妊娠・出産というイベントの際にすぐに予防・治療が必要なのではないかと感じるようになりました。
さらに、より産婦人科領域での活動を増やすことになりました。ご縁もあり、産婦人科の身体機能健診も行わせていただくようになっています。
(湯田)
人との繋がり(ご縁)の重要性を感じます。
ちなみに私が田舎中先生と初めてお会いしたのは、15年ほど前に先生のご講演を聞かせて頂いた時でしたが、その時には既に骨盤底筋群の話をアメリカの情報も含めてされていましたよね。
(田舎中先生)
色んな方を見ています。午前中は介護予防で要支援1または2のかたのグループでの運動指導を行っています。
午後は完全に自費で、コンディショニングを行っています。
比較的私は女性のクライアントさんが多いかもしれません。最近は、産後の骨盤を見てほしいとか、尿漏れがあるということで、ご自分でWEBで検索していらっしゃる方が増えてきています。整形外科医や泌尿器科医の先生から紹介でいらっしゃる方もいます。
疾患で見ている方というと、意外かもしれませんがCVAの方もみてます。
腰痛、骨盤帯疼痛、股関節痛、尿漏れは比較的多いかもしれません。
(湯田)
介護分野、自費部門、様々なクライアントさんに対応されているのですね。
(田舎中先生)
骨盤底機能障害のクライアントさんは、どこにかかればいいかわからないと悩まれている方も多いです。
産後で骨盤が痛いけれど、これは産婦人科なのか?整形外科なのか?また尿漏れがあるとこれは泌尿器科なのか?産婦人科なのか?といった感じです。
この両方に対してコンタクトして対応できるのが理学療法士であると考えています。
(湯田)
同感です。
(田舎中先生)
私自身は長くこういった方々を見させていただいていますが、ウィメンズヘルスをという言い方は実はあまり好きではありません。
おそらく皆さんもOAの方やCVAの方、たくさん見てこられていると思います。
その中で、例えば高齢女性の患者さんで、妊娠・出産を経験している方がいた場合、その妊娠出産では体がどのように変化したのか、開腹術をしていたらその影響を考えますよね。
これもウィメンズヘルスだと思います。
ウィメンズヘルスの視点をもってクライアントさんに接する!これが重要なのではないでしょうか?産前・産後や骨盤底機能障害のみがウィメンズヘルスではないと思うので…
(湯田)
自分も、ウィメンズヘルス=産前・産後というイメージは確かにありました。
「ウィメンズヘルスの視点をもってクライアントさんに接する」なるほど、先生が広い視野をもって理学療法士として様々なクライアントさんに対応されていることに繋がりました。

(田舎中先生)
決して私はうまく両立していると思っていないです・・・
毎日ドタバタですし。ただ、基本的にはなるようになる!と思い毎日楽しむのみです。
(湯田)
先生らしいですね(笑)
(田舎中先生)
子供の年齢それぞれで大変さもありますよね。
私も次女の産後に長女と同じ保育園に入れず、半年ほど2か所の保育園の送り迎えをしました。
この時は保育園の時間も勤務時間と合わず、勤務時間を時短にさせてもらったり、ファミリーサポートやベビーシッターを併用していました。
職場のスタッフの理解や周りに助けて頂きながらなんとか乗り切った感じですね。
(湯田)
職場のサポートはとても重要ですね。
(田舎中先生)
また小学校になるとこどもの学校のPTA活動もとても大変でした。じゃんけんで負けて110番委員長なるものを引き受けなければならず、毎週末学校に行く日々もありましたね。
今は一番大変なのは、週末の予定です。
私の予定、小学校、中学校、主人の予定を確認して学会や講習会などの調整をしています。こどもとの時間も大切にしたいとは思うので、ほどほどにしようとは思っていますが・・・
(湯田)
本当に頭が下がります。
簡単なことではないと思いますが、先生のように努力をされ、楽しみながら家庭と仕事を両立させようとされている姿勢は、特に女性理学療法士の励みになると思います。
貴重なお話をありがとうございました。
次回は、若手療法士についてお話を聞かせて頂けたら思います。