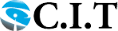C.I.Tセミナー:脳のシステム障害と脳画像からの臨床展開
今回は、千里リハビリテーション病院副院長の吉尾雅春先生をお招きし、脳のシステム障害と脳画像からの臨床展開と題し、脳画像や機能解剖から脳卒中患者に発生する様々な問題へのアプローチについてご講義いただきました。冒頭は、現状の日本におけるリハビリテーション(人間としての復権)の在り方について、「常識を疑う良識を持つ」「原因があって結果がある」と、受講生へ問題を投げかけ、リハビリに対する熱いメッセージを送っていただきました。
具体的な症例を通して、医療者の関わり方が患者様の予後に大きな影響を持つことを改めて認識させられました。患者様にとって良くも悪くもセラピストは大きな環境因子です。患者さんの最大限の能力を引き出せるように努めることが使命だと思わされるイントロダクションでした。
講義の本題は、大脳の機能局在(前頭葉など)や大脳基底核(視床や被殻など)や神経回路(皮質脊髄路、網様体脊髄路など)の機能解剖を解説していただきました。視床が感覚の中継点だけでなく、様々な機能を持ち大脳の全体に投射し、前頭連合野が辺縁系など様々な部位と連絡し、遂行機能に大きな影響を及ぼすことなど、具体例を加えて解説いただきました。また、小脳機能は運動(失調など)だけでなく、前頭連合野と深い結びつきがあり、認知遂行機能にも大きな関連があり、その障害である小脳性認知情動障害(CCAS)を踏まえたアプローチが大切だと示していただきました。
そして、姿勢制御については、皮質網様体脊髄路が非麻痺側の姿勢制御を行うため立位・歩行に大きな影響を及ぼすことや延髄網様体系が繰り返す練習することで下肢の自動運動を代償する可能性を示していただきました。最後に肩関節や股関節の機能解剖についてもご講義いただき、日常の臨床の疑問を払拭できる大変充実した2日間だったと思います。
吉尾先生は、「レッテルを貼るのがセラピストではない、可能性を見出すのがセラピストの仕事である」と言われていました。脳卒中患者は個別性が高く介入は難しいと思います。しかし、脳画像から可能性を見出すためのヒントを沢山与えていただき、明日からの臨床に勇気が湧く講習会でした。